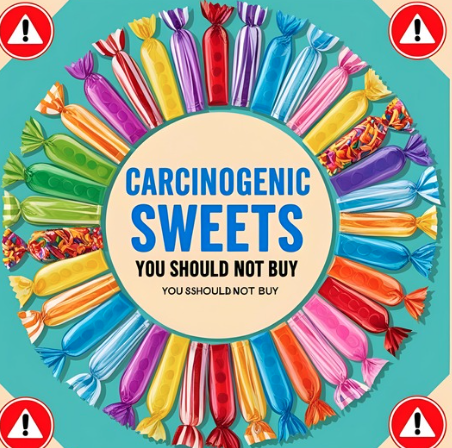
お菓子は手軽に楽しめる存在ですが、健康面で注意すべき点もあります。
中には発がん性の疑いがある添加物を使ったものも含まれているんです。
特に着色料や保存料など、見た目や日持ちを重視した成分に注意が必要です。
たとえば「赤色○号」や「BHA」などは、海外では規制されていることもあります。
こうした成分が入ったお菓子を、知らずに日常的に食べている人も少なくありません。
この記事では、避けたいお菓子の特徴とその理由を、わかりやすくご紹介します。
体に優しい選択をするためのヒントとして、ぜひ最後まで読んでみてください。
買ってはいけないお菓子の特徴

合成着色料を含むお菓子のリスク
合成着色料は、お菓子の色を鮮やかに見せるために使われます。ただ、アレルギー反応や子どもの多動性障害に影響する可能性があるとも言われています。特に、赤色40号や青色1号など、一部の着色料は注意が必要です。フランスの研究では、超加工食品に含まれる添加物ががんリスクを高める可能性も示唆されています。お菓子を選ぶ時は、成分表示をよく確認し、できるだけ天然の着色料を使用したものを選ぶのがおすすめです。
人工甘味料の健康影響と注意点
人工甘味料は、低カロリーや糖質ゼロの商品に多く使われています。例えば、アスパルテームやスクラロースが代表的です。一見ヘルシーに思えますが、腸内環境の悪化や血糖値の乱れ、食欲増進のリスクも指摘されています。さらに、一部の研究では、過剰摂取が肥満や生活習慣病の原因になる可能性も示されています。自然由来の甘味料や無添加のお菓子に切り替えることで、より安心して楽しめます。
酸化防止剤・保存料とその危険性
酸化防止剤や保存料は、食品の品質を長持ちさせる目的で使用されます。お菓子にもよく使われるベンゾ酸ナトリウムやソルビン酸カリウムは、アレルギー反応や過敏症の原因となる可能性があるとされています。また、長期間摂取すると健康リスクを高めるという意見もあります。特に、発がん性の危険性が指摘されているため、成分表示に注意して選ぶことが大切です。
高温調理で生じる有害物質に注意
お菓子の製造過程で高温調理が行われると、トランス脂肪酸やアクリルアミドなどの有害物質が発生します。これらの物質は、心臓病やがんのリスクを高める可能性があり、長期間の摂取は健康に悪影響を与えます。特に子どもは影響を受けやすいので、できるだけ高温調理されたお菓子は控える方が安心です。
お菓子に含まれる具体的に危険な添加物

1. 人工甘味料
- アスパルテーム(E951):摂取しすぎると神経障害や発がんリスクの可能性。
- スクラロース(E955):加熱すると有害物質が発生し、腸内細菌に悪影響を与える可能性。
- アセスルファムK(E950):発がん性の疑いがあり、長期摂取は危険。
ジュースやガムには、高果糖コーンシロップや人工甘味料が含まれることが多いです。アスパルテームやスクラロースなどはカロリーが低いですが、腸内環境を乱したり、食欲を増進させたりする可能性があります。さらに、ガムには人工着色料も含まれていることがあり、これが多動性障害やアレルギー反応の原因になる可能性もあります。特に子どもには、注意して与えることが大切ですね。
2. 合成着色料
- タール色素(赤色102号、赤色40号、黄色5号、青色1号など):発がん性やアレルギー、子供の多動性障害(ADHD)の原因になる可能性。
合成着色料の中には、特に子どもへの影響が心配されるものがあります。
例えば、赤色2号や黄色5号といったタール色素は、多動性障害(ADHD)のリスクを高める可能性が指摘されています。
これらはチョコレート菓子やジュース、キャンディーなどに使用されることが多いです。集中力への悪影響が心配されるので、自然由来の着色料を使用した商品を選ぶと安心です。
3. 保存料
- ソルビン酸カリウム(E202):長期摂取で発がん性や肝機能障害のリスク。
- 安息香酸ナトリウム(E211):ビタミンCと反応するとベンゼン(発がん性物質)を生成する可能性。
4. 酸化防止剤
- BHA(ブチルヒドロキシアニソール)(E320):発がん性の疑いがあり、内分泌系に悪影響を及ぼす可能性。
- BHT(ブチルヒドロキシトルエン)(E321):動物実験で発がん性が示唆されている。
お菓子に使われる添加物の中には、発がん性が疑われる成分もあります。例えば、保存料として使われるベンゾ酸ナトリウムや亜硝酸ナトリウムです。
これらは長期間摂取すると、細胞の変化を引き起こす可能性が指摘されています。
フランスの研究では、超加工食品の過剰摂取ががんリスクを高める可能性が示されています。成分表示を確認して、不要な添加物を避けるのが安心ですね。
5. 乳化剤・増粘剤
- ポリソルベート80(E433):腸内細菌のバランスを崩し、炎症性腸疾患を引き起こす可能性。
- カラギーナン(E407):腸の炎症を引き起こし、発がんリスクがある可能性。
6. 発色剤・防カビ剤
- 亜硝酸ナトリウム(E250):胃の中でニトロソアミンという発がん性物質を生成する可能性。
- プロピオン酸カルシウム(E282):腸内環境を悪化させる可能性。
7. 乳化剤・加工デンプン
- リン酸塩(E450, E451, E452):カルシウムの吸収を妨げ、骨粗しょう症のリスクを高める。
8. 香料・調味料(人工添加物)
- グルタミン酸ナトリウム(MSG, E621):過剰摂取で神経毒性のリスクや中毒性がある可能性。
- アセトアルデヒド:発がん性の可能性がある香料成分の一種。
これらの添加物は特に大量に摂取した場合、健康リスクが指摘されています。お菓子を選ぶ際は、成分表示を確認し、できるだけ自然なものを選ぶと良いでしょう。
9、トランス脂肪酸
マーガリンやショートニングを使ったお菓子には、トランス脂肪酸が含まれることがあります。これは悪玉コレステロールを増やし、心血管疾患のリスクを高めるとされています。例えば、市販のクッキーやパイ生地などに使用されていることが多いです。
最近では日本でもトランス脂肪酸を減らす動きが進んでいますが、まだ完全に排除されているわけではありません。購入する際は、成分表示で「加工油脂」や「ショートニング」をチェックすると安心です。
保存料が多く含まれるお菓子
長期保存できるお菓子には、ベンゾ酸ナトリウムやソルビン酸カリウムといった保存料が含まれていることが多いです。これらは、カビや細菌の繁殖を防ぐために使われますが、体内での分解が難しく、過敏症やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。特に、子どもやアレルギー体質の人は注意が必要ですね。添加物を避けたい場合は、無添加のお菓子や手作りのおやつを選ぶと安心です。
安全なお菓子の選び方
無添加・オーガニック製品を選ぶ際のポイント
安全なお菓子を選ぶポイントは、無添加やオーガニック製品を意識することですね。無添加のお菓子には、人工的な保存料や合成着色料、人工甘味料などが含まれていません。これらの添加物は、長期間摂取すると健康リスクが指摘されているものも多いです。例えば、合成着色料はアレルギーや多動性障害の原因になる可能性があります。だからこそ、原材料がシンプルで産地が明記されている商品を選ぶと安心です。
食品添加物の少ないブランドを知ろう
食品添加物の少ないブランドを知っておくと、さらに安心です。自然派食品を扱うブランドや、オーガニック認証を受けたメーカーの製品は、安全性を重視して作られています。インターネットの口コミや購入者のレビューも参考になります。私も、新しい商品を試すときは必ずレビューをチェックしています。
子どもの健康を守るお菓子選びの工夫
特に子どものお菓子選びには気をつけたいですね。子どもは大人より体が小さく、添加物の影響を受けやすいんです。だからこそ、合成着色料や保存料を避け、糖分量にも気を配ることが大切です。私は子どもと一緒に成分表示ラベルを見ながら選ぶことで、自然と食品の安全性について教えるようにしています。こうした工夫を積み重ねることで、家族みんなの健康を守れると感じています。
